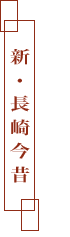 |
|
第二十回/長崎くんちと踊り町 |
|
|
長崎の町は、1571年の長崎開港当初は6か町であったが、以後、その数は増加、江戸時代のはじめ、1630年代には66か町となった。そして、1634年、長崎くんちが始まると、66か町の内、出島町は、オランダ人の町ということで除外、丸山町と寄合町の両町(りょうちょう)は遊女町であるから毎年奉納ということで、これまた除外、残った63か町を踊町(おどりちょう)として21か町ずつ3組に分割した。
江戸時代のくんちは、9月7日が前日(まえび)、後日(あとび)と呼ばれた9日とともに踊や出し物の奉納があったが、中日(なかび)と呼ばれた8日は、踊や出し物の奉納はなかった。 |

▲江戸町での奉納踊り |
|
|
|
そこで、21か町の内、11か町は前日に、10か町は後日にそれぞれ奉納することとして、3組なので3年に1巡された。
しかし、3年に1巡と、踊町が終わったと思うと、すぐ踊がやって来るということで、息つく隙もなかった。
そこで、1655年、3組だった踊町を6組とし、今年は11か町、次の年は10か町、その次の年は11か町というように、11か町、10か町、11か町、10か町、11か町、10か町、11か町、10か町と、6年に1巡とした。
これだと6年に1巡であるから一息つけるというわけである。
そのようななか、1663年、上筑後町、現在の玉園町1帯から出火した火災は、66か町の内、63か町が類焼、なかでも57か町は壊滅的打撃をこうむった。 |
|
|
|

▲桜町方面での庭先回り |
驚いた幕府は、すぐさま長崎の復興に取り掛かり、最新の都市計画を導入、町並を整備した。そして、たとえば浜町は大きいので東浜町と西浜町に、築町も大きいので東築町と西築町に、古川町はもっと大きいので、本古川町と東古川町、西古川町と3つに分けるなど、大きな町を2つ、もしくは3つに分け、踊町を63か町から77か町と、14か町増やした。
|
|
|
|
この14か町の増加によって踊町が6年に1巡から7年に1巡、それも毎年11か町の奉納となり、くんちがスムーズに行われるようになった。
現在でも踊町は、7年に1巡であるが、これは1672年に始まり、現在に至っているのである。
このようにして1672年、長崎の町は総町(そうちょう)77か町に丸山・寄合町の両町(りょうちょう)、さらに出島町を合わせて80か町となり、明治になるまでその数が変更されることはなかったのである。
※写真はイメージでその時代を反映するものではありません。 |
|
|
|
|
|
NPO法人長崎史談会会長 原田博二 |
|
|
|
長崎今昔トップに戻る >> |